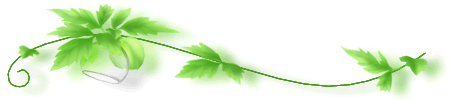|
そういって女は改めて名乗った。 「私は氷の精霊、レセリア。冷たき氷の世界の住人。生き物に死を与える眠りの冷。」 「そう、だったんですか。こっちこそすいません。あまりにも冷たくて驚きました。」 「こちらこそ、人に対する配慮を忘れていたことに対してお詫びするわ。」 そういって、改めて彼女についていくことになり、そこであったのは、ゆうと名乗る女だった。 何でも、彼女も雪女という冷たい世界の住人だとか。だが、氷の精霊であるレセリアよりも、人に近い生活や体温も見せかけでできるようで、低体温だなと思える程度の普通の人だった。 表面上は。 「で、要件は何だ。何かオマケつれてるからそっち関連か?それとも…」 「その心配はないし、残念なことに服は今日はないの。で、要件はこの子だけど…何も覚えていないみたいで、私の花壇の付近うろつかれて困ったからつれてきたのよ。」 花壇という規模ではなかったと思うが、彼らの中ではあれは花壇のようなので、ツッコミはいれないで黙っておくことにした。 「確かに、おかしな魂であることは事実だね。」 「おかしな魂…?」 自分のことがわからないだけに、その意味を図りかねるボクは首をかしげることしかできない。 「レセリアの結界を通れる時点で、『生きている人間』は除外だし、力の弱い私たち側の『特殊な一族』でもない。けど、人の魂に限りなく近い、けれど人と呼ぶには異質な魂。」 レセリアがわからなくて当然なぐらい、かすかな違い。それが何であるかと言葉にしようとして、雪女は急に口を閉ざした。 「悪いな。いうのは簡単だが、本人の前で簡単に言えることではない。このあたりにいられるってことは、公認だろうから、望みがあるのなら、しばらくふらふらしててもいいと思うよ。」 そういって、一人だけ納得している状態に、ボク同様理解していないレセリアさんも文句を言う。だが、言わないとしか答えてくれなかった。 けれど、ボクが何者かわかる人がいてよかった。存在しないと言われたら少しショックだ。 それに、望みの為にしばらくふらふらしてもいいと言われたのが嬉しかった。何だか自分が何者かわからないだけで、とても不安定で、いてもいいのかわからなかったからだ。 ボクが幸せをかみしめているとき、突然… |