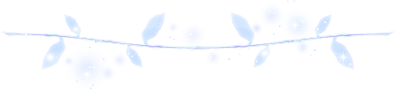
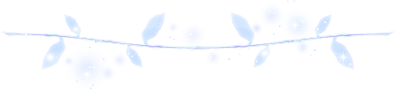
|
二 再会と別れの歌 蒼は強い日差しが差す中、今も砂漠を歩いていた。 太陽の光と身体を砂に埋める北風が蒼を襲う。しかし、普段よりはまだ大人しい。 日が、少し傾いた頃、蒼は小さな街についた。 「あんた、旅人かい?」 「ええ、まぁ。」 曖昧な答えを返して、早々とその場を抜け出す。 今晩はここで泊まろうと、一軒の宿屋に入った。 「いらっしゃいませ。」 見るからに作り笑顔であるカウンターの人間。よく、そこまで笑顔が出せるものだと感心してしまう。 「こちらでお泊りですね。一拍でよろしいでしょうか?」 「はい。」 部屋の鍵を渡されて、蒼は真っ直ぐ部屋に行った。階段を上りだした頃、晩御飯はどうするかと言っている気がするが、無視をした。 あまり、人と関わりたくなかったのだ。
しばらく、眠りについていた蒼はふと目を覚まし、ベッドから起き上がった。 「もう、夕暮れか・・・。」 窓の外からは綺麗な夕焼けが見えた。結構な時間眠っていたようだ。 蒼は目を擦りながらベッドから立ち上がり、唯一ともいえる旅の荷物を手にとった。 蒼は、旅の中で何度も演奏し、歌ってきた。 太陽が支配するこの地には、もう一つの支配者がいる。それは北風である。よく、風の便りで知らせが来るというものがある。もしかすると、愛してくれた母や助けてくれた友が生きていて、どこかで聞いてくれるかもしれない。密かな期待の元、蒼は演奏し、歌い続けてきた。 少しの可能性であっても、諦めたくは無かったからだ。一度、諦めた蒼にとって、二度三度諦める事は同じだが、もう一度会って言いたい事があったために、今度は諦めなかったのだ。 蒼は静かにベッドに腰を下ろしてヴェルダを構え、弓を弦に添えて演奏し出す。 優しい、そして寂しい音楽が部屋に響く。暖かく包み込んでくれるようで、厳しい辛さを感じるメロディ。 曲にあわせて、蒼は歌い出す。 “ 野原で見つけた小さな花、昔の記憶が蘇る 幼い頃、まだ争いを知らない白い頃 愛してくれた母、助けてくれた友 安らぎと温もりを思い出す ” 蒼の歌は宿屋から外へ流れ出す。誰もが、その前を通り、足を止めて聞いた。 “ 乾く涙、泣く事を忘れてしまった そんなある日、再び涙が流れ出す 心に涙が帰ってきた 君と再会できた事で、何かを見つけた その日から、涙は心の中に溜まった そして、涙が流れる時は、いつも君がいて 後にも君がそばにいて、はげましてくれた 一緒に生きるという喜びを知った ” 蒼は、歌い終えた後、静かに演奏を止めた。彼の目には涙が溜まり、ツーッと頬を伝って床に落ちた。 歌うたびに思い出す。母や友、仲間の事を。この歌は、蒼が住んできた村で作られ、何年もの間歌い継がれてきたものである。 多くの人の声と記憶、思い出が詰まった歌である。 そして、その村で暮らしてきたものとわかる証明するものでもある。 いつか、蒼は自分と同じように生き残った仲間と出会う事を願い、今日も歌った。 次の日の朝、少し早い目に旅に出る事にした。 「チェックアウトですね。」 男は手際よく書類に書き込み、ありがとうございましたと一礼した。 外に出た後、蒼は次の目的地までの距離と方向を確認すべく、砂漠横断屋を訪ねた。 「いらっしゃい、今日はどちらへ?」 愛想よく男が出迎えてくれた。 「いや、ただ道を聞こうと思って・・・。」 「そうか、でも、砂漠横断は大変だぜ?あ、おかえり。今日は早いな。」 蒼の後ろにはいつの間にか別の青年がいた。この男の話し方から言って、同業者の仲間といったところだろう。 「あ・・・。」 その青年は、口をあけて目を丸くし、人差し指を蒼に向けて固まる。 「お前・・・。」 いきなり失礼な奴だなと思いつつも、次の行動を待つ。 「どうした?こいつと知り合いか?」 「あの、少し奥へ行っていてもらえますか?」 「なんだい?どうした。」 「いえ、ちょっと確認しておきたい事があるんです。」 男は少し考えて、10分だけだぞと言い、奥へ引っ込んでいった。 「・・・で、何のようですか?」 「一つ、聞きたい。お前の名前、“蒼”じゃないか?」 ビクッと反応する蒼。初対面の人間にいきなり名前を当てられたのだからしょうがない。 「やはり、蒼なんだな?」 「・・・そう、だが。お前、誰だ?」 相手のことを知らずして、疑うなと言うのは無理にきまっている。蒼には、本当にこの青年のことがわからないのだ。 「なんだ、わからないのか?」 「・・・。」 少し寂しそうに言う青年。知らなかったことにショックを受けているのだろう。さすがの蒼も少し戸惑う。 「しょうがない奴だな。お前の事は、一度も忘れなかったし、捜していたというのにさ。ま、お前はあの日のまま変わっていないからわかったのかもしれないがな。」 やはり、この青年は蒼のことを知っている。でも、まだ蒼は思い出せなかった。 「確かに、俺は少し変わったよ。お前はあの日のままで変わっていないよ。でも、親友だったのなら、わかってほしかったよ、蒼。」 親友という言葉にひっかかる蒼。必死に記憶の中を駆け巡り探す。 そして、親友である、会いたかった人物と目の前の青年とを合わせる。 「・・・本当に、流衣なのか?」 似ても、似つかわないが、どこか懐かしい感じがして面影が所々残っている。 「・・・やっとわかったか?でもま、俺は変わりすぎたけどな。」 流衣の言うとおり、あの日とはまったくもって別人である。年月によるものではない。 「俺は、この前ここに来た商人からお前が生きていることを知ったんだよ。歌ってたんだろ?あの歌。お前が一番好きな歌で、得意な演奏をつけて。」 届いていた。自分が必死になって繋ごうとしていた一本の糸が。このメロディが繋いでくれた。 「なぁ、俺はお前に会いたかった。ずっと一緒だという約束を守りたかったんだ。だから、俺はここを出るからさ、一緒に旅に連れて行ってくれないか?」 「でも、仕事なんだろう?」 「いいんだよ。初めから、人を捜していて見つかるまでだと言っているからな。見つかったのだから、出ても問題は無い。」 流衣は相変わらずのようである。蒼の顔から笑みがこぼれた。 懐かしいあの日の中に戻ったかのようであった。 その日、蒼と流衣は親方に一晩泊めてもらった。そして、次の日出発する事にした。 「元気でな、流衣。蒼の旦那、こいつのこと頼みます。」 「なんだよそれ。」 子ども扱いをされて怒る流衣。それも当たり前か。一人前の男としてみてほしい年代なのだろうから。 「俺の、大事な息子だからな。何があっても、二度と離れるなよ?」 蒼と流衣の二人は見送る親方に一度手を振り、その後振り向かずに歩いて行った。 流衣は涙をこらえ、我慢しているように見えた。 それもそうだろう。流衣にとっても、親方は大切な家族同然だったのだろうから。自分が旅をしている長い間、流衣は親方と時間を過ごしてきたのだから。 「・・・本当に良かったのか?」 「・・・いいんだよ。初めから、このつもりだったからな。」 彼は限界だったのだろう。親方もろとも町が見えなくなった頃、大粒の涙を目から零した。 蒼の胸の中で、声を上げて泣いた。蒼は久しぶりに流衣の涙を見た気がした。彼は、何かが起こっても、ほとんど涙をみせなかったからである。 蒼は、涙を見せたときは、何も言わずただ側にいるようにしている。 右手を頭にのせ、子供をあやすようになでてやる。流衣はきつく蒼の服を握り締める。 「大丈夫、すぐに、いつもの俺に戻るから・・・。」 その後、彼はすぐに涙を止め、本当にあの日と同じ彼に戻っていた。 「ありがとうな、いつも、俺の涙を受けてくれて。」 蒼はかける言葉を捜すが見つからない。 だが、今はお互い再会できた喜びで別れも涙も忘れた。 これから続く未来を一緒に話しながら、長い道のりを再び歩き出した。
|