|
その日、ヨルデカートの広場に子どもが集まっていた。 「ネファンスさんが来られているんですね。」 滅多に街に姿を見せない魔女とも呼ばれる老婆がそこにいた。彼女は月に何度か食材の買出しにこのヨルデカートの中央通りに姿を見せる。そして、この広場で子どもを集めて昔話や冒険物語など、様々な話を語るのだ。 魔女と呼ばれても嫌われておらず、彼女は子どもに語り聞かせるだけで、街の者からすれば忙しい合間の子守婆さんとも呼ばれて親しまれていた。 何度も、街はずれのオルノフェアの森の近くに住んでいる彼女に街中へ来ないかと誘ったが、自分はここが静かで落ち着くのだと言うので、皆が彼女の様子を気遣いながら今に至る。 そして、数日振りに姿を見せた彼女に、子どもが婆ちゃんと声をかければ、ぞろぞろと集まってくる。 そして、今日は何の話を聞かせてくれるの?と目を輝かせて言う子ども達に、ネファンスは絵本を取り出して、広場のベンチに腰掛けて語り始めるのだった。 その光景をマリアネアは買出しの際に度々見かけるので、今日がその日かとまだ時間があるために聞いていこうと思った。 「先に荷物持って戻ってくれるかしら?」 「えー。」 フェウスに荷物を預けて先に帰ってもらおうと思ったが、彼も話に興味を持ったらしく、帰る気配はない。 「じゃあ、二人で寄り道しましょうか。」 「おう。」 うれしそうに尾を振りながら、子どもと同じように目を輝かせるフェウスの背中を追い、ネファンスの側まで近づいた。 「これはこれは。教会のお嬢さんとお兄さん。」 「お久しぶりです。」 「婆ちゃんは今日も元気そうだな。」 「長生きだけが取り得だからねぇ。」 三人でたわいもない話をしていると、子ども達から話はまだと文句を言われ、すいませんと謝って彼女の語る話に耳を傾けるのだった。
|
|
|
これは昔々のお話です。 あるところに山にかこまれた村がありました。 その村にりおという子どもがいました。 そのりおは生まれた時から目が見えませんでした。 両親も周囲もかわいそうにと言いました。 けれど、りおはそれを不幸とは思いませんでした。 ある日のこと。危ないから外へ出てはいけないと言われていたにもかかわらず、子どもは出かけて行きました。 何も見えないので、ふらふらして、たまに転びながらも、進みました。 めったに出られない外に出たので、転んでもわくわくした気持ちしかありません。 進めるだけりおは進むのでした。 そして、山への道へと足を踏み入れたのでした。 ふわりふわりと蝶が、まるでりおを導くように集まり、飛びます。 りおはというと、蝶が見えているのか、追いかけるように進みました。 |
 |
|
しばらく歩き、りおは足を止めました。 「誰かいるの?」 りおは問いかけました。 しかし、返事はありません。 そして、いつの間にか蝶もいなくなってました。 「誰もいないの?」 もう一度問いかけると 「子どもよ。ここへ何しに来た?」 今度は返事があった。 「わかんない。歩いていたらここに来たの。」 りおは素直に答えると、ふむっと相手は何か考え、りおに言った。 「ここはわしの寝床じゃ。」 「あなたのおうち?」 |
 |
|
「ごめんなさい。」 すぐに謝って立ち去ろうとすると子どもの肩に触れる手があった。 「こら、待ちなさい。」 何?と振り返る子ども。 「わしは今、起きたところで暇じゃ。」 「寝てたの?」 「そうじゃ。じゃから、話し相手になっておくれ。」 「いいよ。」 「そうか。」 相手に連れられるまま進み、何かの上に座った。 そして、村の事や知人の事、いろいろ話した。 |
 |
|
「そうか、お前は無が見えぬ故、外に出れんのじゃな。」 「うん。」 「見えるようになりたいか?」 「・・・うん。でも、これでもいいの。」 見えないのにも慣れたからと言えば、相手はたまらない。 暗闇の世界が光に満ちた。 「えっと・・・。」 目の前には面を頭につけた人がいた。 「見えるじゃろ?」 「うん・・・。あなたが治してくれたの?」 「そうじゃ。そういえばお主の名を聞いておらんかったの?」 「あ。えっとりお。」 「めいか。良い名じゃの。わしは天狗じゃ。天狗の神無月じゃ。」 天狗と聞いてりおは驚きました。 村の言い伝えで知っていましたが、合えるなんて思ってもいなかったからです。 「もし、何かあればわしの名を呼べば答えてやろう。」 |
 |
|
その日から見るようになったりおに両親も兄も喜びました。 しかし、しだいに村人達も両親も気味悪がりました。 「あの子はあの日、神隠しに会ったのよ。」 「きっと、あの子は化け物よ。」 そして、りおはまた一人でいる事が多くなりました。 |
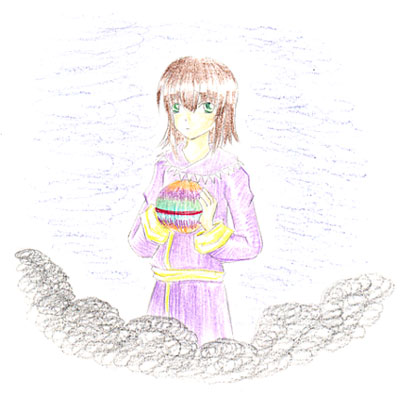 |
|
「りお。」 兄だけは、毎日顔を出してくれてます。 「お兄ちゃん。お仕事は?」 「休憩中だから様子見に来たんだ。」 「そうなんだ。」 「これをあげよう。」 と、兄はりおの髪にリボンをつけました。 それにりおはお礼を言いました。 他愛もない話をして、兄は仕事に戻って行った。 |
 |
|
その繰り返しだったある日のこと。 「大変だー!」 どうしたんだろうと、窓から外を覗くと信じられない事を聞いたのだった。 「・・・が怪我して右目見えなくなったぞ!」 「きっとあの子の目の代償だ。」 「なんということだ。」 追い出すべきだと騒がしくなる。 りおはそんなことより兄の事が心配でしょうがなく、兄のいる仕事場へと走るのだった。 |
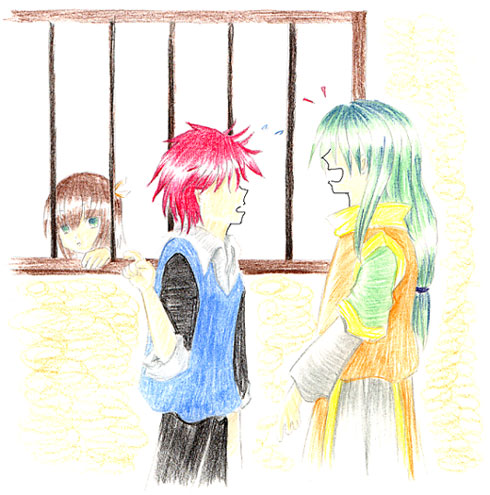 |
|
「お兄ちゃん!」 「りお・・・か?」 兄の側に駆け寄ったりおを抱きとめようとした兄を遮る大きな腕があった。 |
 |
|
「あっちへ行ってなさい。」 疫病神っと、ヒステリー気味に叫ぶ母親にビクッと体が強張る。 「しばらくゆっくり休むのよ、いいわね。」 と、母はもうりおを見ず兄を見る。 自分のせいで兄がこんな事になったんだと思い込み、両親からいらない子だと思われたと思い込んだりおは、村人達の目を見て怖くなった。 |
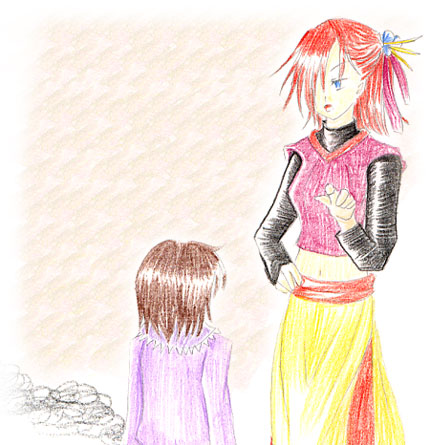 |